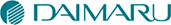佐藤 壮馬 美術家
目の前のリンゴがゆらめきながら映し出す光と影、札幌の記憶
2025年7月29日の営業終了後、6階の休憩スペース・グリーンパティオに、新しいアート作品が運び込まれました。大きなシラカバのテーブル中央に並ぶ5つのリンゴは、気鋭の美術家・佐藤壮馬さんの「Entangled Dimensions:縺れた次元(もつれたじげん)」の作品です。かつての瑞々しいリンゴの姿を留める透明な樹脂に閉じこめられているのは、かじられて腐ったその後の姿。イスに腰掛けて作品をのぞき込むと、赤みを残すリンゴがレンズのような樹脂の中でゆらゆらと心に迫ってくるようです。この作品の舞台は、かつてリンゴ園から遊郭へと姿を変えた歴史が残る札幌市白石区。なぜリンゴ?どうして白石区??佐藤さんに、作品制作までの道のりを伺いました。
取材者:大丸札幌店 村田大樹
佐藤 壮馬 さとう そうま
美術家
恵庭市出身、39歳。高校卒業後に上京し、青山スタジオ(東京)で撮影に従事。2010年に渡英し、2011~2012年ロンドン大学(UCL)人文科学ファンデーションコース (近代西洋文学及び芸術史・人文地理学・批判理論専攻)修了、2012~2015ロンドン大学(UCL)バートレット校建築学部建築学科 中途退学。3Dスキャンを用いたアーティスト集団ScanLAB Projectsに従事した後、2020年に活動拠点を北海道に移す。近年の主な活動に、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出(2020)、KyotoSteam2022(京都市京セラ美術館)、第16回shiseido art egg賞グランプリ(2023/資生堂ギャラリー)、VOCA展(2025/上野の森美術館)など。

6階の休憩スペースで
ゆっくりアート鑑賞を
綠の植物と白い木肌が美しいシラカバ家具が並ぶ休憩スペース、グリーンパティオの空間で、ひときわ目を引く艶やかな5つのリンゴ。この作品は、北海道恵庭市出身の美術家・佐藤壮馬さんが手がけた「Entangled Dimensions:縺れた次元」の作品です。
このリンゴに留められている札幌の歴史をおさらいすると……。
明治初期、札幌の街外れだった薄野には札幌遊郭がありました。薄野の市街地化に伴い移転が計画されると、リンゴの病害虫で悩んでいた当時の白石村の果樹園主たちが手を挙げ、用地の寄附によって遊郭誘致を実現させます。1920(大正9)に移転が終わった札幌遊郭には30軒ほどの妓楼(ぎろう)が建ち並び、土地の名前から白石遊郭とも呼ばれるようになりました。戦後の法改正で妓楼は姿を消し、今では住宅地へと様変わり。ちょうどそのエリアに佐藤さんが住んだことが、作品制作の大きなきっかけになりました。
佐藤さんの創作活動を支えているのは、写真、建築、3Dスキャン、場所との関係性といった、一見繋がりがないようで、しっかりと繋がっている経験の積み重ね。リンゴの作品が生まれるまでの道のりといえる、佐藤さんのこれまでをかけ足で振り返ります。

「高校卒業後に上京し、撮影スタジオで働きはじめました。ちょうど僕らは、現像が必要なフィルムカメラからデジタルカメラの技術に移行する最初の世代。カメラのレンズを通して対象を見ながら、目の前に広がっている空間について考え始めていた気がします。当時は映像を扱う写真家や、写真家が枠を広げてデジタルアートの分野にも進出していて。10年、20年先を考えて、僕も空間を扱えるようになりたいという漠然とした思いがありました」
実践により技術を身につけた佐藤さんは、あらためて学ぶ機会を得るために、学生それぞれのバックグラウンドを生かした教育内容が魅力的だったロンドン大学建築学科への留学を決意。徹底的に英語を学び、渡英したのは20代前半のことでした。

ロンドン大学への留学時に
出会った3Dスキャン
「1年次は、デジタルの作画は一切やらせてもらえません。その場に行って、それぞれの目に留まるものを探すんです。例えば、ロンドンには赤い電話ボックスがあって、街の象徴的な存在として都市の中に点在しています。バッキンガム宮殿や大英博物館のように、イギリスがアイデンティティーを主張するような場所にビシッと並んでいるのですが、街外れや住宅街だとただの四角い箱型で、『この場所ではこうあってほしい』という恣意性が感じられますよね」
そんなある日、佐藤さんは建築学部の棟のエレベーター内で、3Dスキャンの技術を使って街をスキャンするワークショップの貼り紙を見つけて参加します。

「テーマは、『乗り物が知覚する街』。自動運転車には、対象との距離を測る3Dスキャンのレーザー光を使用して、ターゲットの表面までの距離を測定するライダーという技術が使われています。道路を走る車と運河を走行するボートにライダーを取り付けて、対象物から跳ね返った距離をXYZの座標軸の点の集合が形として認識するんです。異なるスピードで街をスキャンし、それをどのように表現するか考えるワークショップは、参加者同士和気あいあいとしながらも、とてもクリエイティブなことに取り組む楽しい経験になりました」
メンバーに誘われて大学を1年間休学して活動に取り組んだ佐藤さんは、その後、3Dスキャンのアーティスト活動に本腰を入れるべく大学を中退します。
「スキャンの仕事は計6年ほどやっていました。イタリアに1カ月滞在してはロンドンに帰ってくるといった具合に、行って帰ってを繰り返しながら各地を飛び回る一方で、場所に対して希薄な感覚になっていることも感じ始めていて。そんな時にコロナ禍のロックダウンに突入し、次のステップに踏み出そうと考えて約15年ぶりに北海道へ拠点を移すことに決めたんです」

経験と技術、思考と感覚が
積み重なったリンゴの作品
故郷に拠点を移した佐藤さんは、場所や物事にしっかり向き合う感覚を得ながら、大雨の日に倒木した岐阜県の神明神社のご神木を3Dスキャンし、歴史や信仰、慣習との関係性を表現する作品づくりに取り組みます。物語や歴史は尊く、大切にしなければならない思いがあると同時に、それが原因で悲惨なことも起こりうる。そんな物語性に思いを巡らせている頃、札幌のバスセンター近くにあるギャラリー『空間』での展示が決まります。
「僕が住んでいる菊水からギャラリーまで行くには、豊平川に架かる一条大橋を渡ります。『この橋はいつからあるのかな?』という素朴な疑問から調べてみると、ちょうど僕が住むエリアに遊郭があったことを知りました」
自分が暮らす土地に、かつては遊郭があった事実。同じ場所にも、時代を越えてさまざまなレイヤー(層)がもつれるように折り重なっている感覚。さらに制作に取り組んでいた2023年10月にハマスがイスラエルを攻撃し、土地に紐付く歴史や物語が現代を縛り、人々の感情を動かしながら、ときに残虐な行為に及んでしまう現実を見せつけられます。
「リンゴの中に腐ったリンゴを入れる形を思いついたのは、ポンペイ遺跡でスキャンした仕事に影響を受けています。灰に埋まった人の石膏像をCTでスキャンすると、歯や指輪が残っているんです。肉体はなくなっているのに確かな痕跡がある。もとある形と、朽ちて腐ったものとの関係性が、僕の中に強く残っていて。外にある幻想のような捉えがたいもののあり方は、きらびやかに見える遊郭の女性の苦しい心の内や、幻想と現実のギャップにもつながるかもしれないと考えました」

佐藤さんの人生が積み重ねてきた技巧とコンセプト、現代を生きながら感じてきた思いをぎゅっとまとめるプロセスで生み出されたのが、この「Entangled Dimensions:縺れた次元」です。
「作品を通して、自分が一人称的に捉える目の前のモノやコトの先にある、いろんなレイヤーや、もつれを考えるきっかけになったらありがたいです。通りすがりに『これは何だ?』と見ていただいて、誰かの記憶に残ったり、誰かの人生が良い方向に動き出したりするかもしれない可能性が、常設展示によって初めて生まれた気がします」
佐藤さんの作品の常設展示は、光栄なことにグリーンパティオが第一号。リンゴと向き合うと、美しいと感じる心の底の歪みを問われるようで、気持ちが静かに揺さぶられます。ぜひみなさんも、リンゴとの語らいを通してご自身の心と向き合い、街の歴史に思いを馳せるひとときを心ゆくまでご堪能ください。

※本記事の情報は、2025年7月のものです。