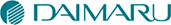石川 朋佳 トヅキ合同会社
人生の歯車は そばの町・幌加内で 回り始めて
自分が働こうと思った時、世の中にある職業の中から選ぶことが圧倒的に多いのではないでしょうか。今回ご紹介する石川朋佳さんは、自身が願う生き方を仕事にしようと動き出している女性です。ある時は「そばを打つ人」、ある時は「まちづくりコーディネーター」、そしてある時は、「幌加内ソバ循環プロジェクトプロデューサー」etc.として。2024年には、トヅキ合同会社を設立し、そばの未利用資源を活用した「そば甘皮茶」やそば殻で染めた衣料品などの商品開発、高校生と共に地域課題を解決するための商品づくりプロジェクトなど、幌加内町の“そば”を軸に、地域と食に向き合う生産者を応援し、思いを届ける活動に取り組んでいます。ひとつの肩書きでは収まらないない役割の真ん中にあるのは、幌加内で出会った人たちへの恩返しの気持ち。作付面積、収穫量ともに日本一のそばの里・幌加内に通いながら、理想の生き方に仕事を重ねていく石川さんに話をお聞きしたくて、7月の幌加内町へ向かいました。
取材者:大丸札幌店 藤尾智美
石川 朋佳 いしかわ ともか
トヅキ合同会社代表社員
札幌市出身、26歳。幌加内町ソバ循環プロジェクトプロデューサーとして、地域の食資源を余すことなく活用し、人とおいしさと向き合いながら未来へ続く地域づくりの活動に取り組む。トヅキの由来は、人が生まれるまでの期間である「十月十日」、十月生まれの石川さんと、十日生まれの師匠から。
幌加内での高校生活が
人生の大きな転機に
「『そばを打つ人』、『まちづくりコーディネーター』、『ソバ循環プロジェクトプロデューサー』……。私の肩書きは、その場によって変わるんです」と石川さんが言うように、彼女の取り組みは、世間一般にある職業名では収まりません。
そば粉で作るお菓子の「HOROKA-幌菓-」やそばの甘皮茶などの商品開発、そば殻染めのアパレルブランド「kirinomi」を主宰するほか、そば打ち体験のイベントや地域と食の講演など、衣食住を軸にして、未来へ続く地域をつくるための商品開発や企画づくり、つまりは仕事そのものを生み出す人でもあるからです。

「農業に興味を持ったのは、中学校の修学旅行の時でした。岩手県の農家さんでお手伝いをさせていただいたんですね。3時のおやつで食べた四角いお餅のようなお菓子がとてもおいしくて。体を動かして、大地の恵をいただく暮らしの営みすべてが当時の私には衝撃的で、『こういう暮らしがしたい!』と思うようになりました」。
給食と部活のバレーボールのために学校へ通っていた中学生が、修学旅行で出合った農業は進路を決める道標に。農業を学ぶ札幌圏の高校へ進学することになった石川さんは、入学前の春休みからバレーボールの練習をしに学校へ通うほど、高校生活を心待ちにしていたそうです。
「新入生代表の挨拶でスタートを切った高校生活は思い描くようにはいかず、人生のレールから外れてしまった罪悪感がありました。環境を変えなければという思いから、寮生活しながら農業を学べる学校を探して見つけたのが北海道幌加内高校だったんです」。
「人生で一番大きな選択だった」と石川さんがふり返るこの選択が、運命の舵を大きく切り、思いもよらぬ出会いへとつながっていくのですから、人生とは本当に不思議なものです。

プロジェクトの始まりは
坂本さんのひと言
石川さんが進学した北海道幌加内高校は、道内外から生徒が集まる町立昼間定時制の農業高校です。一次 (生産) × 二次 (加工・製造) × 三次 (流通・販売) = 六次産業化を学ぶ教育を軸にしており、なにより驚くのは、必修科目に「そば」の授業があること!生徒たちは、全麺協が主催する「そば道段位制度」の初段以上の取得を目指して、座学や実習に取り組みます。
「『そば』の授業でお世話になった外部講師のひとりが、現在、そば道段位の最高位である七段位を持つ人生の師匠であり、経営の大先輩である坂本勝之さんでした」。

必修科目に加え、石川さんが所属したそば打ちの部活「そば局」を通して、ふたりは交流を深めます。当時目指していたのは、全国高校生そば打ち選手権大会で1位になること。
8月に東京で行われる大会に向けた合宿では、真夏の暑さに負けないようにジェットヒーターを焚いて猛特訓。努力の結果が実を結び、石川さんは高校3年生の時に「第7回全国高校生そば打ち選手権大会」の個人戦と団体戦で、見事、優勝を果たします。
「とことん向き合ってくださった人たちに、恩返しをしたかったのかもしれません。坂本さんや先生が大会についてリサーチし、粉の挽き方からそばの細さまで調整しながらご指導くださって。周囲の方に勝たせてもらえたのだと、今になって気づきます」。会場にクーラーが付いていたことも、今となってはよい思い出です。
6次化産業を体感しながら学んだ幌加内高校を経て、石川さんは異なる角度から農業を見るために、小樽商科大学の商学部へと進学します。高校での実践を大学では理論として学び、時にはギャップも感じながら、インターンなどにも積極的に参加。卒業後は、社会人としての経験を積むために、空調器機を扱う建築業界のメーカーに就職します。そして数年が経った頃……。

トヅキの思いに
共感の輪が広がって
「製粉作業の際に出てしまう、そばの甘皮やそば殻などの廃棄物を活用できないだろうか」。
社会人になってからも幌加内と深く関わっていた石川さんは、坂本さんがふとこぼした言葉をしっかり心で受け止めて、未利用資源を活用した商品企画や、生産者と消費者、田舎と都市を双方向からつないで循環させていくビジョンマップを描き上げます。
「坂本さんから出された、初めての宿題のような気持ちでした」と石川さんがふり返る答え探しが、今につながる「幌加内ソバ循環プロジェクト」の芽吹きとなりました。

「幌加内ソバ循環プロジェクト」は共感を呼び、さまざまな企業や団体からの後押しを得ます。2024年3月にはトヅキ合同会社を設立してプログラムを本格化。未利用資源を活用した商品開発や、異業種とそばのコラボレーションイベント、幌加内高校とベンチャー企業による未利用資源を活用した新商品開発や、助成金を活用する「そばストーリーツアー」のような地域プロデュースなどにも取り組み始めました。
「今は何でも挑戦して、やってみる時期。継続できるもの、収入を得るベースをしっかりと作れるようにしていきたい」と、石川さんは力を込めて前を向きます。人生の出会いと経験が織りなすトヅキの取り組みは動き始めたばかり。
幌加内の未来をつくり出そうとしているおふたりから感じられたのは、生産者と消費者、農村と都市のように、異なる立場や世代を超えて受け渡す知恵と発想が生み出す力の大きさ。そして、大地に根ざして暮らす人の営みや土地の歴史、技を磨き続ける人への敬意の眼差し。幌加内の課題解決への道筋には、北海道の未来に必要なヒントがあるように思えてなりません。

※本記事の情報は、2025年7月のものです。
Events

7階ライフスタイル雑貨イベント
開催期間:2025年8月13日(水)〜19日(火)
場所:大丸札幌店 7階ライフスタイル売場
本イベントには、栄養たっぷりの甘皮を利用したノンカフェインの甘皮茶、サクッホロッの食感が楽しい「幌菓」のそば粉のスコーン、凛とした美しいグレーが特徴のそば殻染めのブランド「kirinomi」の洋服がお目見えします。
※本イベントは終了しました。